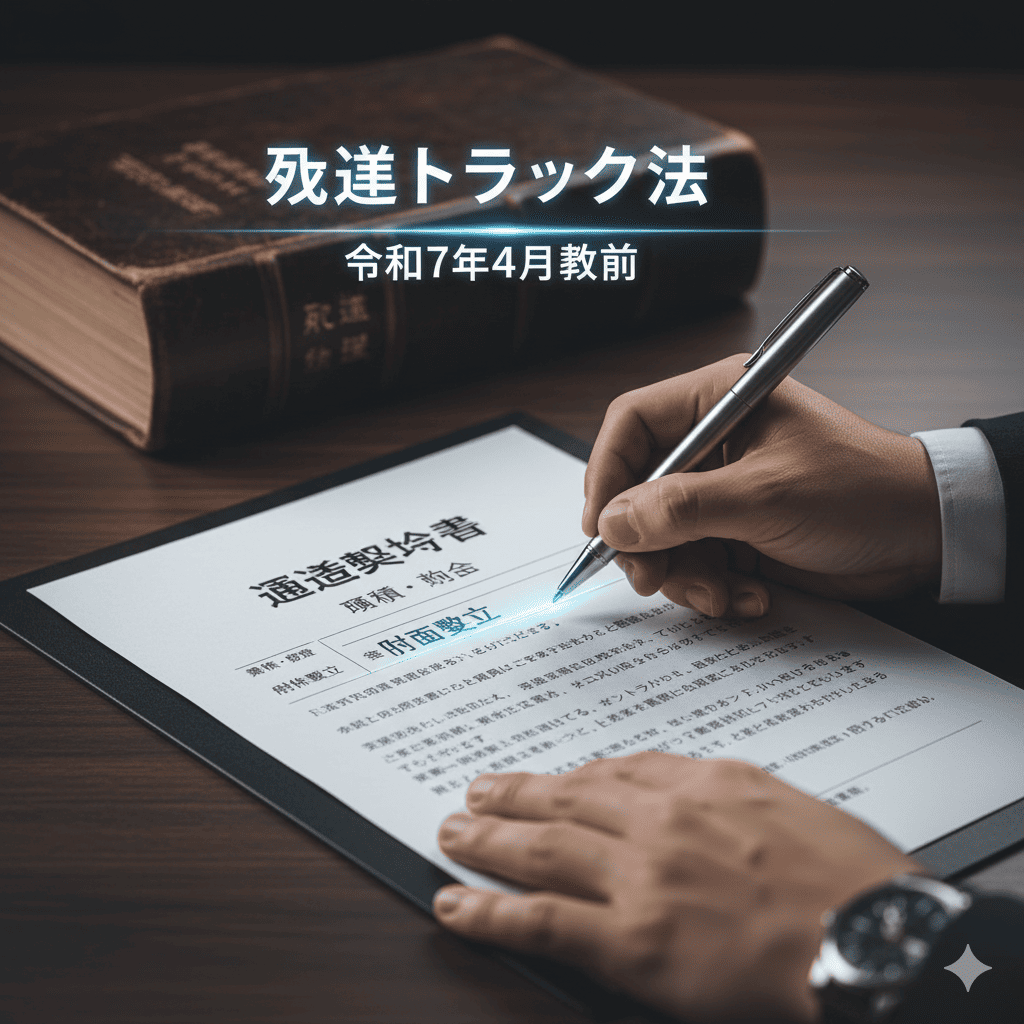事業拡大や欠員補充のため、新たにドライバー(運転者)を雇い入れる予定の運送事業者様へ。
新しい仲間を迎えることは喜ばしいことですが、事業用自動車の運行安全を確保するため、乗務を開始する前には法令で義務付けられた多数の手続きや教育を完了させる必要があります。
このチェックリストを活用し、行政処分リスクを回避しつつ、安全運行の基盤をしっかり築きましょう。
【最重要】雇入れ前の「見極め」が、最大のリスク管理
これらの手続きを始める前に、経営者として必ず行うべき、最も重要なステップがあります。それは、面接段階での徹底したヒアリングと、内定を出す前の裏付け確認です。
新しいドライバーに安心してハンドルを任せるためには、以下の3点を必ず確認しましょう。
- 運転記録証明書の提出を約束させる
- 面接時に、採用が決まった際には提出が必要であることを伝え、同意を得ておきます。
- 過去の事故歴・違反歴を正直に申告してもらう
- 「記憶にない」は通用しません。記録証明書で全て明らかになることを伝え、正確な情報を求めます。
- 業務に支障をきたす可能性のある病歴の有無を申告してもらう
- 安全な運行に直接関わる、非常に重要な項目です。
そして、最も重要なのが、これらの申告内容と、後日提出される書類の間に、少しでも食い違いや嘘が判明した場合は、雇用契約そのものを白紙に戻すという毅然とした姿勢です。
口頭で内定を伝えた後でも、「正式な雇用契約は、必要書類に問題がないことを確認した上で締結します」と明確に伝えておくこと。この一手間が、後々の大きなトラブルから会社を守る、最強の防御となります。
ドライバー個人の適性を見る前に、事業者として必ず行わなければならない、法的な雇用手続きがあります。これを怠ると、後々大きなトラブルに発展しますので、最優先で実施しましょう。
チェックリスト1:最優先!労務関係の基本手続き
ドライバー個人の適性を見る前に、事業者として必ず行わなければならない、法的な雇用手続きがあります。これを怠ると、後々大きなトラブルに発展しますので、最優先で実施しましょう。
| 手続き | 実施内容 | 法的根拠/留意点 |
| 雇用契約書の締結 | 労働時間、賃金、休日、業務内容などの労働条件を明記した書類を、必ず書面で取り交わします。口約束はトラブルの元です。 | 労働基準法 |
| 労働保険の手続き | 従業員を一人でも雇用した場合、労災保険・雇用保険への加入は義務です。管轄の労働基準監督署、ハローワークで手続きを行います。 | 労働保険徴収法 |
| 社会保険の手続き | 法人事業所や、常時5人以上の従業員を使用する個人事業所は、健康保険・厚生年金への加入が義務です。管轄の年金事務所で手続きを行います。 | 健康保険法、厚生年金保険法 |
チェックリスト2:雇入れ時の基礎情報把握と健康管理(要保存)
運転者を雇い入れたら、まずは過去の運転経歴や健康状態を確認し、記録・保存する義務があります。
| 手続き | 実施内容 | 法的根拠/留意点 |
|---|---|---|
| 運転記録証明書の取得 | 自動車安全運転センターから過去3年間の運転記録証明書を取得します。 | 証明書の取得に時間を要する場合でも、申請手続きが行われたことを確認した後であれば、乗務を開始しても差し支えありません。 |
| 事故歴の把握 | 雇い入れた者の過去3年間の事故歴を把握します。 | 把握すべき事故は、事業用自動車によるものに限りません。無事故・無違反証明書または運転記録証明書により把握します。 |
| 雇入れ時の健康診断 | 常時使用する労働者に対し、医師による11項目の健康診断を受けさせます。 | 医師による健康診断を受けた後3月を経過しない者を雇い入れる場合で、その結果を証明する書面を提出したときは、当該項目は省略できます。 |
チェックリスト3:義務付けられた運転適性診断の受診
運転者は、国土交通大臣が告示で定める適性診断(初任診断など)を受診することが義務付けられています。
【プロのヒント】予約は「内定後すぐ」が鉄則! 適性診断は予約が混み合っていることが多く、いざ受診させようとしても数週間先まで空きがない、というケースが頻繁にあります。これでは、ドライバーの乗務開始日が大幅に遅れてしまいます。
対策は一つです。面接が終わり、内定を出したその日のうちに、すぐに予約を入れましょう。最近はインターネットで簡単に予約手続きができますし、トラック協会の会員であれば、費用はかかりません。この一手間が、事業計画の遅延を防ぎます。
初任診断の留意点ですが、これはあくまで原則であり、以前の診断結果を保管している場合や前の職場から取寄せられる場合なので実質的には雇い入れたら新たに受けてもらうのがベストです。
| 運転者の区分 | 受診すべき診断 | 留意点 |
|---|---|---|
| 初任運転者(原則) | 初任診断 | 過去3年以内に初任診断を受診していれば、その診断結果をそのまま使用できます。 |
| 事故等を引き起こした者 | 特定診断Ⅰまたは特定診断Ⅱ | 特定診断を受診させた場合、初任診断を受診させたものとみなして差し支えありません。この場合、添乗指導を除く6時間の事故惹起者教育を実施し、記録・保存が必要です。 |
| 65歳以上の者 | 適齢診断 | 適齢診断を受診させた場合、初任診断とみなして差し支えありません。受診結果に基づき特別指導を行い、記録・保存が必要です。 |
チェックリスト4:初任運転者への特別な教育(合計35時間以上)
運転経験が浅い、または経験ブランクがある「初任運転者」は、安全規則に基づき、合計35時間以上の特別な教育を受ける必要があります。
1. 初任運転者の定義と対象者
初任運転者とは、当該事業者において初めて事業用自動車に乗務する前3年間に、他の運送事業者等によって運転者として常時選任されたことがない者を指します。
- 履歴書等で、過去3年以内にトラック運送会社での運転経験がないことを確認しましょう。
- 上記の適齢診断や特定診断を受診した者でも、経験がない場合はこの35時間以上の教育が必要です。
2. 指導内容と必須時間
| 指導区分 | 内容 | 必須時間 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 座学(知識) | 法令遵守事項、運行の安全確保に必要な運転に関する事項等。改正された指導・監督指針の12項目を含めます。 | 15時間以上 | |
| 実技(技能) | 実際に事業用トラックを運転させ、安全運転方法を指導します。 | 20時間以上 |
【重要】 実技指導の20時間は、必ずしも十分ではありません。運行の安全の確保に支障がないと認められるまで、指導を継続して実施する必要があります。
3. 実施時期と特例
指導は、原則として当該貨物自動車運送事業者において初めて事業用自動車に乗務する前に実施しなければなりません。
ただし、やむを得ない事情がある場合は、乗務を開始した後1か月以内に実施できます。
- 添乗指導の特例: 事業者が安全な運転に必要な技能を備えていると判断した運転者に対しては、添乗による安全運転の実技に限り、乗務を開始した後1か月以内に指導を実施しても差し支えありません。
4. きめ細かな指導の実施
単に時間をこなすだけでなく、安全運転に必要な知識・技能の向上を図るため、きめ細かな指導が求められています。
- 適性診断の結果を活用し、運転者と話し合いをしつつ指導を実施します。
- 運転者自身が気づかない技能、知識、または運転行動に関する問題点がある場合は、運転者としてのプライドを傷つけないように配慮しつつ、これを指摘することが必要です。
- 指導の終了時には、運転者により安全な運転についての心構え等についてのレポートを作成させるなどして、指導の効果を確認することが望ましいとされています。
チェックリスト5:法令遵守のための記録と行政処分リスク
法令に基づき必要な指導や健康管理を怠った場合、行政処分を受ける可能性があります。
| 記録対象 | 保存期間 |
|---|---|
| 初任運転者教育(35時間以上)の記録 | もれなく記録・保存 |
| 疾病、疲労等のおそれのある乗務に関する記録 | 3年保存 |
| その他一般的な記録(指導監督指針等) | 5年保存 |
行政処分の基準(抜粋)
もし、事業者による指導及び監督が不適切であった場合、運転者が法令違反を犯した際に、事業者が指導監督の責任から処分を受けます。
- 特別な指導の実施状況違反(大部分不適切:2分の1未満実施):初違反で10日車、再違反で20日車の処分を受ける可能性があります。
- 運転適性診断の受診義務違反(受診なし2名以上):初違反で10日車、再違反で20日車の処分を受ける可能性があります。
ドライバーを雇い入れた際には、安全運行のためにも、行政対応のためにも、これらの手続きと教育を確実に実施しましょう。
この記事を書いた行政書士
岩本 哲也
運送会社の経営に携わる、現場経験豊富な現役の行政書士。 法律知識と現場感覚を掛け合わせ、「きれいごと」で終わらない、運送業経営者のための実践的なコンサルティングを得意とする。
▼運送業の経営に関するご相談はこちら [行政書士岩本哲也事務所]